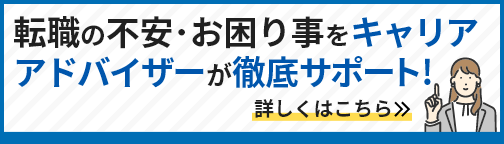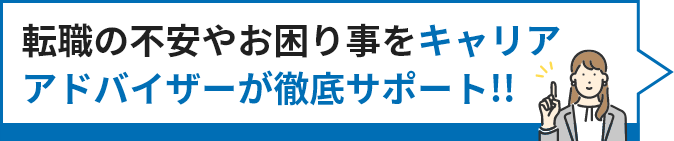設計監理とは?必要な資格や施工管理との違いも
設計と工事の監理業務両方に携わる、設計監理という業務はご存じでしょうか?
設計段階から建築に関わる設計監理業務の概要、必要な資格などを解説します。
建築物を建てる際、設計と工事の監理業務両方に携わる、設計監理という業務はご存じでしょうか。
施工管理とも混同されやすい設計監理は、設計段階からその建築に関わる重要な役割を持っています。
本記事ではそんな設計監理について、その業務の概要を必要な資格などとともにご紹介します。

設計監理とは、建築において建物の設計と工事の監理、両方を一貫して行う仕事です。
建築主とすり合わせながら建築物の詳細な設計を行い、図面や仕様書などに落とし込むというところから、施工が始まれば現場に出向き、設計通りに進められているかを専門的な知識を持って確認する監理業務までを担っています。
図面や設計書だけでは伝わりにくい内容もあるため、そういったものを実際の現場に伝えるというのも業務のひとつですね。
しかし、現場の規模にもよりますが設計監理者は現場に常にいるということは少なく、適宜調査を行うことが多いでしょう。
そのため、その間に大きなトラブルがないよう、現場の管理者に事前にトラブルが起こりうる箇所について通知しておくというのも業務のひとつですね。
「監理」と「管理」の違い
設計監理職が行う「監理」は、「管理」とは意味合いが異なります。
工事の「管理」は、工事をスムーズに進めるためにスケジュールや予算、品質、現場の安全などを管理する業務です。
建設を施工する会社が、現場業務として行うことになります。
一方で設計監理職が行う「監理」は、工事が設計書・仕様書の通りに実施されているのかを現場に出向き確認・修正する業務です。
施工会社ではなく、建築主側の代理人となる建築士が担うものです。
施工管理との違いは?
その名称や同様に現場に携わる仕事であることから設計監理と混同されやすいのが、施工管理です。
大きな違いとして、施工管理は前述の「管理」を行う仕事であるということがあります。
建設を実際に行う施工会社が行う業務で、現場代理人として設計をもとに工事を進めるための現場のあらゆる管理を行います。
現場の確認を行う設計監理とは、業務範囲にもその立場にも違いがありますね。
設計監理の仕事は、その名称の通り「設計」と「監理」の大きく2つの業務に分けられます。
それぞれ具体的にどのような内容なのかをご紹介します。
設計業務
設計業務では、主に以下のような業務を行います。
- 条件の整理
- クライアントへの提案
- 法や条例などに違反しないよう役所との協議
- 設計(基本・実施)
まずは、クライアントの依頼により予算や敷地、法律などの条件を整理し、それにあった外観や設備などの大まかなプランをクライアントに提案します。
大まかなプランが決まったら、建築基準法やその地域ごとの条例に違反しないよう確認し、役所との協議も行います。
それらを加味して、クライアントの要望に沿った実際の設計に入ります。
設計には間取りや構造・設備仕様などを決定する「基本設計」と、その後正確な寸法や細かな仕様を設計する「実施設計」の2つの手順があります。
監理業務
設計が完了しても設計監理の業務は終わらず、監理業務に移ります。
- 見積もりの精査
- 施工会社の選定
- 工事の監理
- 検査
実施設計までを図面に起こした実施設計図面が完成したら、施工会社にその図面をもとに見積もりを依頼します。
見積もりは内容に漏れや誤りがないかを確認し、予算の調整などを行ったのち、それをもとに施工会社を選ぶことになります。
実績や特徴までしっかりと考慮して施工会社が決まったら、とうとう実際に工事が始まります。
工事が始まったら、設計監理者は現場で作業が設計書通りに不備なく行われているかを調査するのが仕事です。
クライアントにも調査結果を報告し、問題がある場合には施工会社側に改善を促します。
完成時にも、仕様書通りに建てられているか最終的な検査を行い、問題なければ引き渡しへと移ることができるでしょう。
設計監理業務を担うためには、国家資格である建築士資格が必須となります。
建築士は業務独占資格であるため、設計監理で必要になる設計図面の作成や工事の監理業務は建築士資格を持っていないと行えません。
建築士資格では建築基準法に則った設計が行える知識を問われ、法規や構造に関する学科試験の他にも、事前に与えられた課題で実際に製図を行う設計製図試験なども行われます。
また、建築士は
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
の3つの種類に分けられており、取得している資格によって取り扱える建造物の大きさなどが異なります。
それぞれの資格でどのような規模の建築物を扱えるかは、以下にまとめています。
| 資格 | 扱える建築物 |
|---|---|
| 一級建築士 | ・延べ面積が500平方メートル以上の公共建築物 ・延べ面積が300平方メートル以上、高さが13mまたは軒の高さが9m以上ある建造物 ・鉄筋コンクリート造/鉄骨造/石造/無筋コンクリート造/コンクリートブロック造・レン瓦/木造 |
| 二級建築士 | ・延べ面積が30平方メートル~300平方メートルで、高さが13mまたは軒の高さが9mを越えない建造物 ・延べ面積が500 平方メートル以下の公共建築物 ・鉄筋コンクリート造/鉄骨造/石造/無筋コンクリート造/コンクリートブロック造・レン瓦/木造 |
| 木造建築士 | ・二階建て以下の木造建築物 |
一級建築士になれば公共事業などの大規模なものまで特に多くの建築物に携わることができますが、その分資格の難易度が高いことでも知られています。
免許登録時にも、履修経験や実務経験、また二級建築士の資格取得などの条件が定められています。
そのため、一級建築士資格の取得を目指す方は、設計監理など二級建築士として実務経験を積んでいくのもおすすめですね。
より詳しい難易度など、建築士資格についてより詳しく知りたい方は、こちらのページもご参考ください。
資格として必須となるのは建築士資格のみですが、設計監理業務を行うには様々なスキルが求められます。
特に重要になるのが、コミュニケーションスキルです。
設計監理者は、建築主や現場の作業員・施工会社側の管理者などとの適切なコミュニケーションにより、建設を設計書通りにスムーズに行えるような監理を行わなければなりません。
トラブル時など、問題を迅速に解決するためには、現場と連携して対応することが求められるでしょう。
また、建築設計の知識の一環として、建築関連の法律や地域の条例などもしっかりと理解しておきましょう。
設計時には、法律を遵守しながらクライアントの要望に応えることが重要になります。
今回は、建築現場で設計から監理業務までを担う設計監理について、その業務や必要スキルなどをご紹介しました。
設計はもちろん、建築主となるクライアントの代理として施工が設計通りに行われているかの監理を行うため、設計監理には建築士資格が必須になります。
特に一級建築士は難易度の高い資格として知られていますが、設計監理は設計の細かな部分を現場に伝える重要な役割を持つ仕事であり、やりがいもあるでしょう。
建築士資格を活かして働きたいという方は、ぜひ建設転職ナビの無料転職支援サービスをご利用ください。
経験豊富なコンサルタントが、あなたの希望や意向をもとに活躍できる企業をご提案致します。
執筆・編集
建設転職ナビ編集部
建設転職ナビ編集部では、長く建設・不動産業界に特化した転職サービスを提供しているヒューマンリソシアの知見と最新情報を元に、建設・不動産業界で活躍していきたい皆様へ有益な情報を発信していきます。
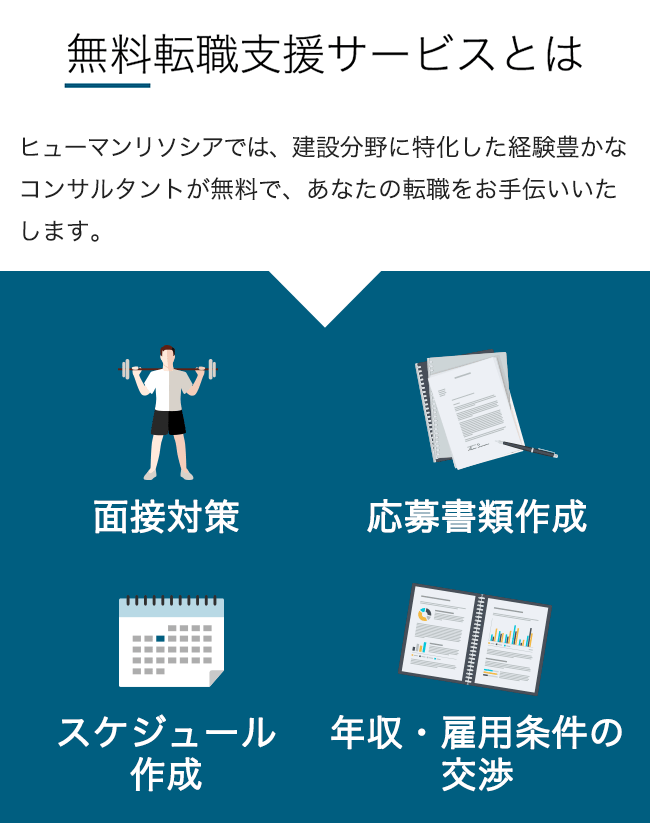
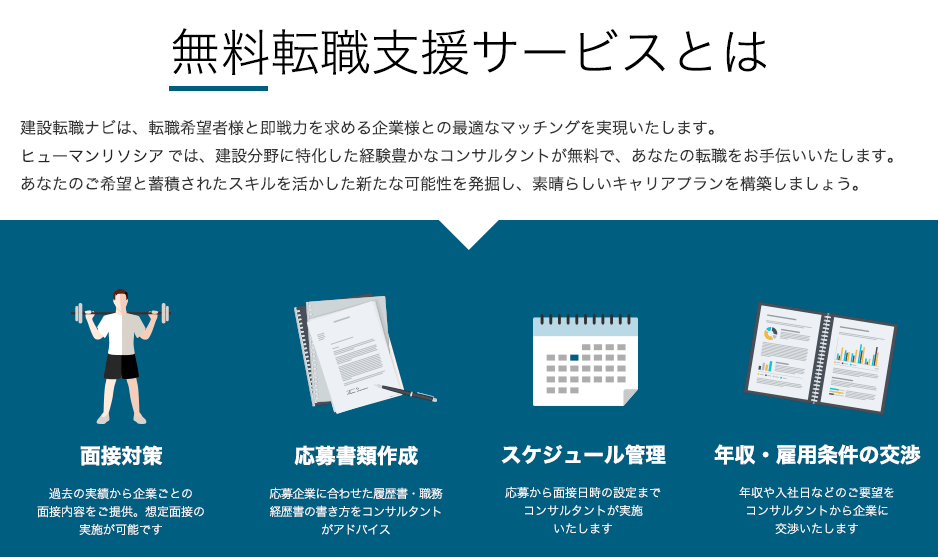
建設業界に精通したコンサルタントが徹底サポート!!
今すぐサポートをご希望の方は
建設転職ナビにご登録ください
-
職種で検索
建築設計 意匠設計 構造設計 土木設計 電気設備設計 機械設備設計 設備設計・その他 建築施工管理 アフターメンテナンス 土木施工管理 電気工事施工管理 管工事施工管理 設備施工管理・その他 造園施工管理 プラント機械施工管理 プラント電気施工管理 プラント土木建築施工管理 プラント施工管理・その他 プラントプロジェクトマネージメント プラントオペレーター ビル設備管理 プラント設備管理 施設管理 建築積算 土木積算 設備積算 発注者支援 測量・点検・調査 コンストラクションマネジメント(CM) プロジェクトマネージャー(PM) 設計監理 確認検査 品質管理 エクステリア(造園)設計 営業職(建築) 営業職(土木・建設コンサル) 営業職(設備) その他技術職 営業職(建設その他) 電気設備保全 機械設備保全 マンションフロント 用地仕入 不動産開発 賃貸管理 アセットマネジメント(AM) プロパティマネジメント ビルマネジメント(BM) 法人営業(不動産) 法人営業(住宅) 個人営業(不動産) 個人営業(住宅) その他専門職(住宅・不動産) -
資格で検索
1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士 1級管工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士 1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 1級電気通信工事施工管理技士 2級電気通信工事施工管理技士 1級建設機械施工管理技士 2級建設機械施工管理技士 1級造園施工管理技士 2級造園施工管理技士 監理技術者 エクステリアプランナー 一級建築士 二級建築士 木造建築士 建築設備士 構造設計一級建築士 設備設計一級建築士 計装士 CAD利用技術者 エネルギー管理士 建築物環境衛生管理技術者 高圧ガス製造保安責任者 危険物取扱者 消防設備士 甲種 消防設備士 乙種 消防設備点検資格者 ボイラー技士 給水装置工事主任技術者 第一種電気工事士 第二種電気工事士 第一種電気主任技術者 第二種電気主任技術者 第三種電気主任技術者 工事担任者 建築積算士 建築コスト管理士 認定コンストラクション・マネジャー 技術士 技術士補 RCCM 測量士 測量士補 地理空間情報専門技術者 地質調査技士 補償業務管理士 土壌汚染調査技術管理者 コンクリート技士・診断士 土木鋼構造診断士 土木学会認定土木技術者資格 宅地建物取引士 管理業務主任者 マンション管理士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建設業経理事務士 労働衛生コンサルタント その他 建設・不動産関連資格 -
都道府県で検索